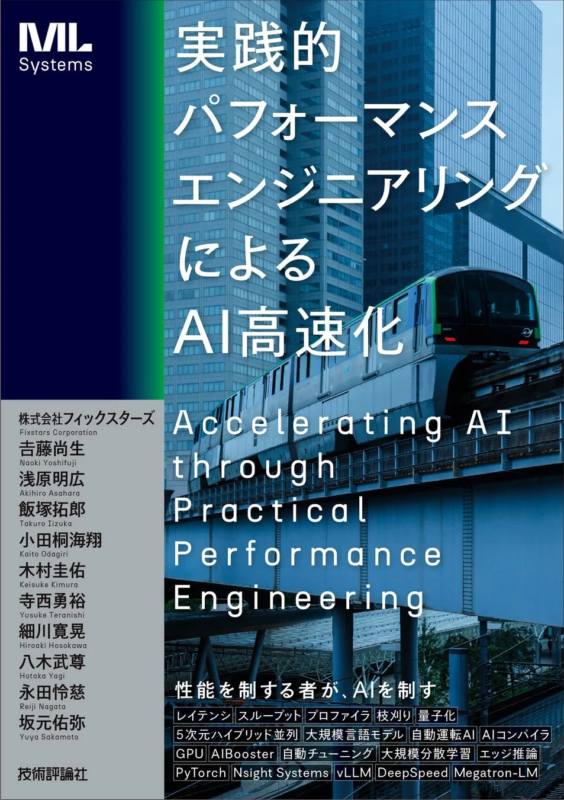AI開発の効率を高める新刊『実践的パフォーマンスエンジニアリングによるAI高速化』が12月22日に発売
AI開発に取り組むエンジニアにとって役立つ一冊として、株式会社フィックスターズのエンジニアが執筆した書籍『実践的パフォーマンスエンジニアリングによるAI高速化』が、技術評論社より2025年12月22日(月)に発売される予定です。この本では、AI処理を速くするための技術について、基本的な考え方から具体的な方法までが解説されています。AIの学習や推論に関わるエンジニアが知っておくべき、コンピューターの計算能力を最大限に活用する方法が紹介されています。
AI時代に欠かせないパフォーマンスエンジニアリング
ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)をはじめとする生成AIやAIモデルは、私たちの仕事のやり方を大きく変えつつあります。これに伴い、GPU(画像処理装置)や電力といった計算に必要となる資源の確保にかかる費用が、企業の競争力を左右する重要な要素となってきました。
「パフォーマンスエンジニアリング」とは、コンピューターの計算能力を最大限に引き出し、実行したい処理を最も効率の良い形に最適化する技術です。フィックスターズは、長年にわたり、ハードウェアの特性からソフトウェアのアルゴリズムまで、プログラムの処理を高速化するための多岐にわたる高度な技術を培ってきました。
AIの重要性が増す現代において、AI処理の精度と速度を最適化することで、IT投資の効果を最大化し、運用にかかるコストを減らすことができるパフォーマンスエンジニアリングは、非常に重要な技術と言えるでしょう。
書籍『実践的パフォーマンスエンジニアリングによるAI高速化』の概要
この書籍では、これまであまり体系的に説明されることの少なかったパフォーマンスエンジニアリングについて、特に現代のAI処理を中心に、基本的な考え方から実践的なノウハウまでが解説されています。
目次
-
第1章:パフォーマンスエンジニアリング概論
-
第2章:まずはパフォーマンスを計測する
-
第3章:次にパフォーマンスを改善する
-
第4章:実践1:LLM 推論
-
第5章:実践2:LLM 事後学習
-
第6章 実践3:LLM(継続)事前学習
-
第7章 実践4:自動運転AI 学習
-
第8章 実践5:自動運転AI 推論
書籍情報
-
書名:実践的パフォーマンスエンジニアリングによるAI高速化
-
著者:株式会社フィックスターズ(吉藤 尚生、浅原 明広、飯塚 拓郎、小田桐 海翔、木村 圭佑、寺西 勇裕、細川 寛晃、八木 武尊、永田 怜慈、坂元 佑弥)
-
出版社:技術評論社
-
発売日:2025年12月22日(予定)
-
定価:3,630円(税込)
書籍出版記念セミナーも開催
本書の出版を記念して、執筆陣によるオンサイト(会場参加型)限定セミナーが開催されます。
このセミナーには、ゲストとして『Data-centric AI入門』の著者である宮澤 一之 氏(GOドライブ株式会社 AI技術開発1部 部長)が招かれ、「AIを速くする技術」と「データからAIの品質を高める方法」の両面から、実際の業務に役立つポイントが伝えられる予定です。
セミナー後には、宮澤氏とフィックスターズの執筆陣との懇親会も企画されており、著者と直接交流できる貴重な機会となっています。
開催概要
-
開催日時:2025年12月15日(月) 19:00 〜 20:30
-
会場:BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 7F HALL3(〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目1−1)
-
参加費用:無料(事前登録制)
株式会社フィックスターズについて
フィックスターズは、「“Speed up your AI”(AIを速くする)」をコーポレートメッセージに掲げるテクノロジー企業です。コンピューターの計算資源を最大限に活用するソフトウェアの最適化技術を使い、AIモデルの推論処理(AIが答えを出す速さ)と学習プロセス(AIが学ぶ速さ)の両方で、非常に高い高速化を実現しています。医療、製造、金融、モビリティなど、さまざまな分野で次世代AI技術の進化を推進しています。
詳細情報:https://www.fixstars.com/